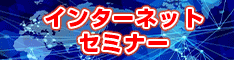基準地価、訪日客需要で4年連続上昇
国土交通省は7月1日時点での都道府県地価(基準地価)は、住宅地・商業地・全用途の全国平均が4年連続で上昇したと発表した。上昇率はいずれもが1992年以降で最大値となった。地方圏はいずれもが3年連続で上昇した。背景には、円安によって海外資金が物流工業用地の建設で流入に加え、訪日客の増加でホテルの新設ラッシュが寄与したことが挙げられている。
米政策金利を0.26%引き下げる
9月17日、米国の連邦準備制度理事会(FRB)は主要政策金利を0.25%引き下げることを決定した。雇用悪化による景気への悪化を危惧し、景気を下支えするため利下げ再開に踏み切った。あと2回開かれるFRB会合で0.5%のさらなる利下げが見込まれている。パウエル議長は「雇用の下振れリスクが高まり、インフレリスクのバランスが変化した」と利下げを決定の理由を述べた。一方、18日の東京株式市場は米国の利下げ決定を受け、4万5303円43銭で取引を終え、史上最高値を更新した。
企業版〝ふるさと納税〟は過去最多に
内閣府は2024年度に「企業版ふるさと納税」制度を利用し自治体に寄付した額は約631億4千万円だったと発表した。額と寄付件数ともに前年度比1.3倍で、制度が始まった2016年度以降で最多を更新した。また、寄付した企業件数や寄付を受けた自治体は過去最多となった。一方、寄付を受け入れた自治体の使い道では、地域産業や観光などの振興といった「しごと創生」が最多の376億円で、「まちづくり」の113億円が続いた。内閣の担当者は「制度の周知・理解が進んだ結果」としている。
家計金融資産、過去最大の2239兆円
日銀の2025年4~6月期の資金循環統計で、家計が保有する金融資産の残高は6月末時点で2239兆円だった。前年比1.0%の増加で、過去最大を更新した。金融資産の内訳をみると、投資信託が9.0%増の140兆円、株式等は4.9%増の294兆円となり、それぞれ過去最大を記録した。少額投資非課税制度(NISA)の普及に伴い投資信託が伸びたことに加え、株価の上昇も家計保有金融資産の増加に寄与したと見られる。一方、現金・預金は個人消費が堅調に推移したことや、キャッシュレス化の進展で0.1%減の1126兆円だった。
介護給付費、過去最高の10兆円後半に
厚生労働省がまとめた介護サービスの利用者負担を除く2023年度の介護給付費は10兆8263億円となり、過去最高を更新した。高齢化を背景に、介護や支援が必要と認定を受けた人は前年度比2%増の708万人と過去最多となり、このうち75歳以上が627万人と大半を占めている。また、65歳以上の高齢者1人当たりの給付費は2.9%増の30万2千円となっている。介護給付費は介護保険制度が始まった2000年度の約3倍に達している。
下水道、全国297kmで道路陥没の恐れ
国土交通省は古く大きな下水道管を全国の自治体が調査したところ、41都道府県の297kmで道路陥没につながる恐れがある腐食や損傷が見つかったと発表した。このうち35都道府県の72kmは原則1年以内の対応が必要となる「緊急度1」の深刻な劣化が確認された。また、225kmの「緊急度2」は応急措置の上で5年以内の対策が必要と判定された。原則1年以内の対策が必要な下水道管の長さを都道府県別にみると、愛知の約14kmを筆頭に、茨城(約10km)、大阪(約9km)が続いた。
米研究機関、「日本の危険な暑さ」22日増
米機構研究機関のクライメイト・セントラルは、地球温暖化の影響により日本で6~8月に観測された「危険なほど暑い日」は62日に上ったと発表した。温暖化がなかった場合に比べて22日増加したと分析している。同研究機関は「温室効果ガスの排出量削減が遅れれば、各地の生態系や経済はより多くの被害を受ける」と指摘している。人口100万人以上の日本の都市を対象にした分析では、広島市の「危険なほど暑い日」は55日で、このうち温暖化影響により増加した日数は31日となり、国内最多だった。
首都圏への本社移転は過去10年で最多
帝国データバンクの調査によると、2025年1~6月に地方から首都圏へ本社機能を移転した企業は200社に上り、過去10年間で最多だったことが分かった。現在のペースで首都圏への企業移転が通年で続けば、1990年以降で初めて400社台になる可能性があると同社ではみており、首都圏への一極集中が強まっていくことになる。地方から首都圏に転入した企業の業種はサービス業の80社が最多で、1990年以降で最多ペースとなっている。次いで、卸売業(34社)、小売業(21社)が続く。